





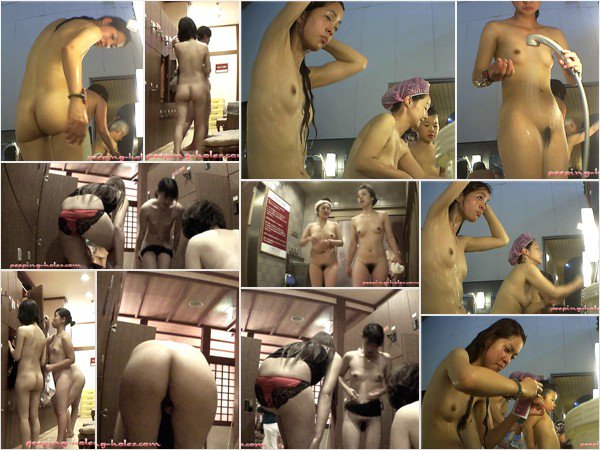
今日の新旧ヒーロー対決は吉田松陰&楠木正成VS岡本太郎だ。
松陰は崇拝する正成が活躍する太平記を読む時、髪を逆立たせ眼を裂けるように開かせ大声で逆賊・足利尊氏を罵ったという。そして高杉晋作ら若い門下生も足利尊氏を憎んで罵った。そして生き残った伊藤博文らの門下生は明治時代の指導者となり教科書にも正成の活躍話を載せ、大東亜戦争において特攻隊の若者たちは若き日の高杉・伊藤らと同じく正成のようであろうとして玉砕していった。
僕も幕末の長州の下級武士の若者として育ったら松陰に感化され楠木正成に憧れたかもしれない。何かワクワクするような心持ちは若き日なら間違いなく持っただろう。だが物事を一面しか見ないことの危険性も理解できただろう。
今のヒーロー岡本太郎はインドをおとずれた時、インドでさえ第二次大戦後の西洋文明の影響を受け画一化された美術を受け入れていることにガッカリした。僕も広い視点を持ちたいものだ。
もっとも松陰の絶体絶命にして無力なのに楠木正成たらんとする心意気は今の自分と重なってきて芸術家として認められている岡本太郎よりはるかに共感できる。太郎は世間の理解など求めておらず、松陰は自分こそが正義だと信じそれを理解しない周囲を憎む独善性はあったが。結果的に松陰の正義が勝利し日本人を戦火へ導くことになったのは間違いない。その中の日本人には岡本太郎もいた。そして太郎は自由を奪われた軍隊生活を生き抜き、僕に夢と自由と希望をもたらした。岡本太郎の勝利だ。






高杉晋作の辞世「おもしろきこともなき世をおもしろく」の話がウソだったという衝撃の情報を知り17歳の若き日に心を熱くしたおーい竜馬の高杉晋作の話を読みなおしている。竜馬は高杉が最期に言ったと伝わる「吉田へ」というのを愛人のおうののところへ行きたいという意味だと言っている。これについては今までの知識でもありえないと思っていたが17歳の時でさえ、何かおかしいなと思い高杉を美化している雰囲気は当時から感じていた。「三千世界の烏を殺し、ぬしと朝寝がしてみたい。わしとお前は焼き山かずら、裏は切れても根は切れぬ」という高杉の歌も実態を知るとゾっとする。この歌は、事実そうなったとおり高杉に敵対する椋梨藤太らを殺し、徴兵制を確立し国民を戦争に行かせて自分は権力をほしいままにした山県有朋へ援軍要請のラブコールをしている歌なのだ。何かおかしいと思っていたあの日から高杉の正体は見ぬいていたが辞世と思っていた句だけはわりと好きだった。たしかに高杉が書いた句ではあるが元々は「おもしろきこともなき世におもしろく」だったらしい。一緒に歌を作っていた人と冗談まじりに軽い気持ちで作った句だということが「を」が「に」に変わっただけで伝わる。「こんなつまらん世の中、どうすればおもしろくなるかのう」とふざけながら言ってる高杉の姿が目に浮かぶ。これは野村望東という尼と合作した句で「すみなすものは心なりけり」と野村が続けた。「心持ち次第で世の中は面白くなりますよ」という意味で愚痴る高杉を諭す意味もあったようだ。






種田山頭火・尾崎放哉の師である俳人、荻原井泉水は「俳句は人である、心境であるということ。作品が芸術なのではなくて、純粋に生きることが芸術なのだということ」と唱えていた。これは岡本太郎の「生きることそのものが芸術」という生きざまに通じる。太郎のその生きざまは「生きることそのものでヒーローになる」という今の僕の生きざまにつながった。井泉水が中心になって行われた「自由律俳句」の活動は季語や五七五の定型にこだわってきた、それまでの俳人の常識をくつがえすものだった。常識を超えていっている点において、岡本太郎に憧れる僕が、同時に種田山頭火・尾崎放哉に心ひかれるのは自然な流れだったのだろう。そして太郎が唱えていた生きざまは、太郎がその思想に到達する以前から山頭火、放哉が実行しており、太郎なき今も僕が実践している。
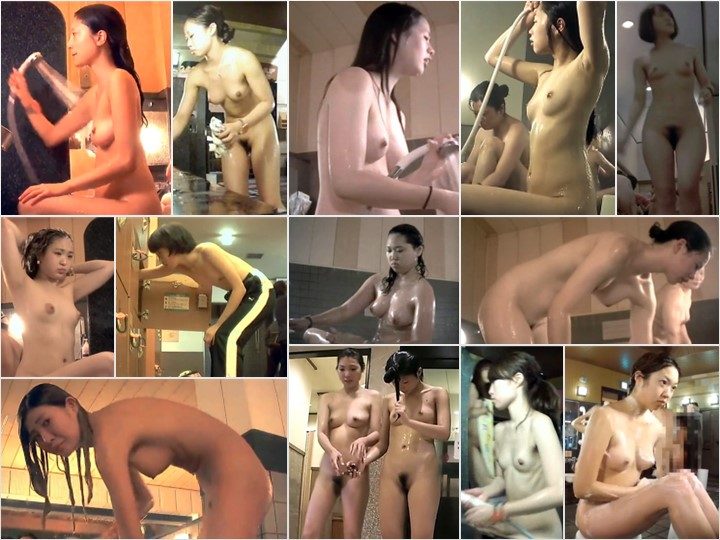





かつての僕の英雄たち、幕末の志士にとっての英雄は楠木正成だった。
月と日の むかしをしのぶ みなと川 流れて清き 菊の下水
湊川の戦いで天皇への忠義を貫いて死んだ正成をイメージして詠んだ坂本龍馬の歌。続いて楠木正成を崇拝する高杉晋作の言葉。
楠木公のような古今にまれなる忠臣も空しく討ち死になさったし、大塔宮は親王のご身分でありながら、讒言によって土窟のに閉じ込められ、ついには、ろくでもない連中の手にかかってお命をお落としになった。
北条泰時、足利尊氏らは姦臣逆賊であるにも関わらず、子孫代々高位に付き、高禄を得、栄華を極めたわけだが、それは一体どういうことなのか。
昔の人が「天道がこれで良いのだろうか」と歎いたのも無理もない。僕も罪があって、この獄につながれたわけだが、獄舎が建てられてから既に100年以上が経っているので、官位はもちろん大塔宮や楠木公には到底及ばないけれども、その心ばえは大塔宮や楠木公と同じように尊く、にもかかわらず、幽囚された人はいたはずだと思うと、ひどく悲しい気持ちになってくる。
堂々たる楠公や大塔宮のような人でも、とんでもない災禍に陥ることがある。また、足利尊氏や北条泰時のような姦臣逆臣であっても、時の流れに乗じた時は、数代に渡って栄華をきわめることもある。このような例は、国、時代、身分の上下に関わらず、いくらでもあるのだ。
戦前は正成が尊敬され足利尊氏は悪人とされていたからやはり終戦前の日本は長州藩士たちの尊王攘夷運動によって作られた天皇の世だったと考えるべきだろう。その中心人物たちの正成を崇拝する歌。
久坂玄瑞 湊川にて
みなと川 身を捨ててこそ 橘の 香しき名は 世に流れけん
高杉晋作
いはんや天地の正気我が神州に鍾(あつ)まれり。人はこれ楠公、木はこれ扶桑、山はこれ不二。
入江九一
桜井の その別れ路も かかりけむ いまのわが身に 思ひくらべて
吉田稔麿
日頃ながさん私の涙 何故に流れるみなと川
真木和泉守
楠公の忠義は天下第一である、その理由はご本人だけでなく、楠公を模範として一族みんなが忠義のために死んだからである。足利氏が皇位を簒奪し皇統が断絶することがなかったのは、楠木氏が最後まで忠義を貫いて奮闘されたからである。皇統ある限り、楠公の忠義もまた天壌無窮ではないか。
近藤勇 小楠公
よしの山 花や匂はむ あづさ弓 引きかえさじの きみがことの葉
長州と敵対していた近藤さえこれである。若い彼らの正成への思いは純粋な部分もあったのだろうが。大東亜戦争で特攻隊の若者たちが突撃して死ぬ前に書いた寄せ書きに湊川の文字があった。
桜花ロケットに人間を乗せ体当たりさせる特攻隊「神雷部隊」隊長だった野中少佐は、桜花を「この槍、使い難し」と評し、出撃を命じられたとき「湊川だよ」と言ったという。
大東亜戦争は悲劇だったという風潮の中で育った現代人の僕は正成に憧れていた史実の幕末の英雄像が、かつて憧れた司馬史観的な革命をめざすものとは違うような感じがしてそれほどいいとも思えない。
やはり岡本太郎や種田山頭火にとってのヒーロー像が好きだ。
ゴッホは絵を描くほかない
何ら他の手段も持っていないのだから
すでにどうしようもないほど追いつめられている
だが彼の夢はすべて破れた
もう彼は世界と断絶するほかない
この男の運命は、実際、何もかもひどかったのだ
生まれてこなければよかった、という他はないほど
轟然と自分の胸に弾丸を撃ちこんだ時、しかし、そのピストルの音とともに、世界はゴッホの前で忽然と変貌した
絶望的な生きがいでありあれほど追い求めた、執着した芸術を放棄した瞬間、彼に初めて人生の、つまり芸術の真の意味がわかったのだ
芸術なんて何でもないのだ
それを見極め捨てたところから、はじめて本当に意味がひらける
芸術に憧れ、しがみつき、恐れ、叫び、追いかける
そのような芸術主義では、ついに『芸術』に達することはできない
誇らしく敗北したまま彼は死んで行った
岡本太郎『美の呪力』より
芭蕉は芭蕉、良寛は良寛である、芭蕉にならうとしても芭蕉にはなりきれないし、良寛の真似をしたところで初まらない。
私は私である、山頭火は山頭火である、芭蕉にならうとも思はないし、また、なれるものでもない、良寛でないものが良寛らしく装ふことは良寛を汚し、同時に自分を害ふ。
私は山頭火になりきればよろしいのである、自分を自分の自分として活かせば、それが私の道である。
私は芭蕉や一茶のことはあまり考えない、いつも考えているのは路通や井月のことである。彼等の酒好きや最後のことである。
種田山頭火
放浪VS幕末
フォーマット付ブログのコツ
導入パラグラフはどんなコンテンツがあるのか読み手にイメージしてもらうことができます。ブログ記事の項目リストでもいいでしょう。フォーマットを使い分ければ、テキストが読みやすくなります。フォーマットについては続きをお読みください。
ブログに画像をつけよう
画像はブログの読み手を視覚的にひきつけるので、読んでもらいやすくなります。コンテンツの最初の画像は自動的にブログのサムネイルとして表示されるので、ブログ記事に関連の深い画像を選ぶと効果的です。


